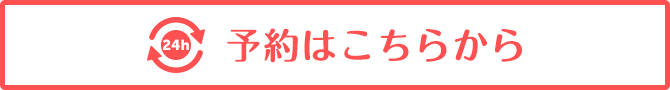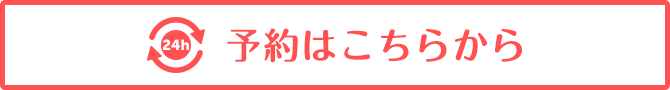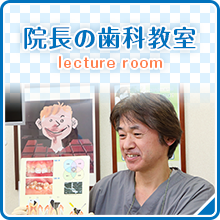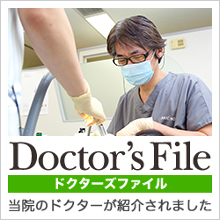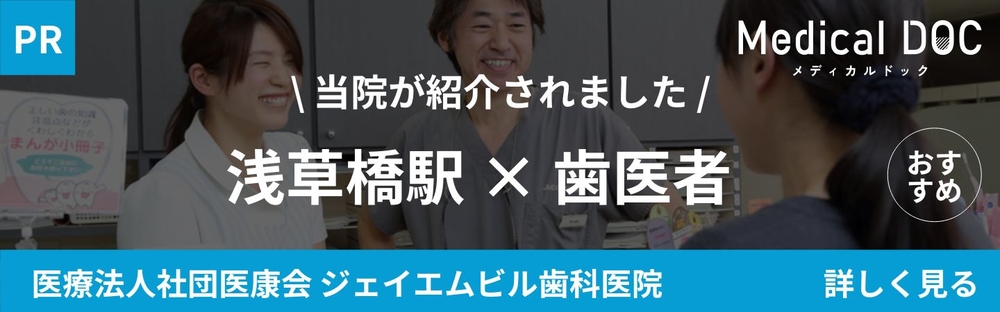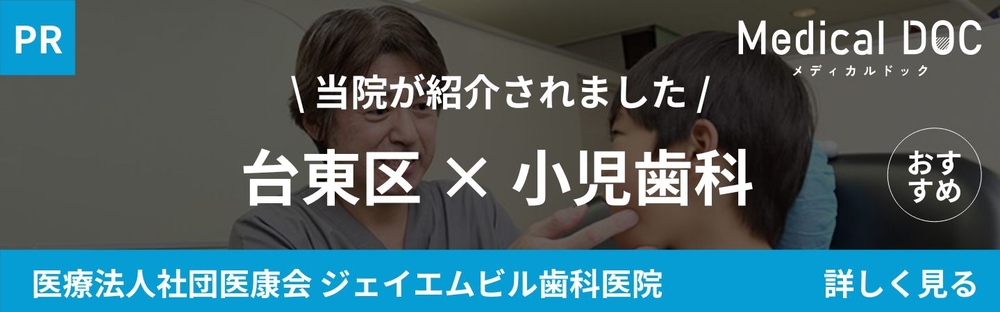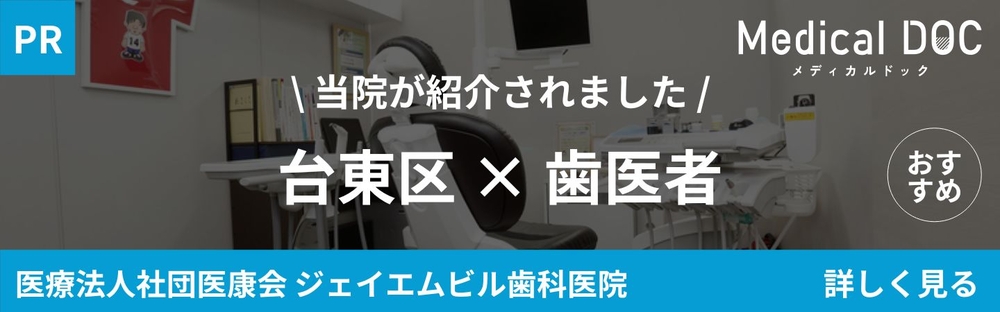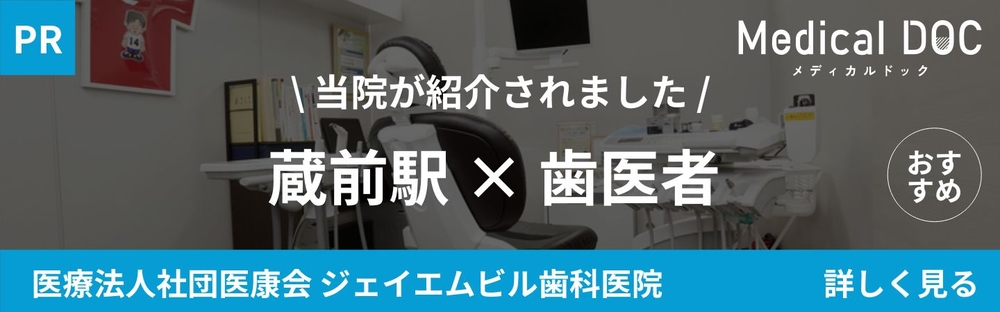しかし、お口の大きさや歯並びは、その人により異なり本来は、お口の状況に応じたものを使わなければ
十分なプラークコントロールは出来ません。
残念ながら、磨き方は歯医者で習った事はあるが歯ブラシや歯磨き剤の選択方法を知る人は、非常に少なく購入するときには、何となく選んでしまう人がほとんどのようです。
よくわからない人は、かかりつけの歯医者に相談し歯ブラシを選ぶと良いかと思います。(当院では、お勧めはしていませんが電動ブラシについても同じことが言えます。)
話がそれてしまいましたが、今では、無数に存在する歯磨きグッズですが、江戸時代にはすでに歯の汚れを取るために色々な工夫をしていました。
歯ブラシの変わりになるものとして、クロモジやヤナギの木を細く削り煮て柔らかくして先端を木槌で叩いてブラシのようにしたもので、「房楊枝」と呼ばれていたそうです。
そして、歯磨き粉も存在し、房州砂という砂の上澄みを乾燥させた微細な砂にハッカなどの香料を混ぜたものでした。
実際に想像して江戸時代の歯ブラシ「想像の房楊枝」作ってみました。
写真は、ジェイエムビル歯科医院院長作です。
せっかく作ったのでためしに磨いてみました。先端に歯磨き剤を付け歯周ポケット付近をなでる様に使うと・・・以外に気持ちの良いものでした。
欠点は、棒状なので歯の裏側は殆ど磨けません・・・
予防歯科の発達した現代に産んでくれた両親に感謝です!
予防に勝る治療はありません!
蔵前 ジェイエムビル歯科医院
院長 野崎康弘
医院案内は、こちらです。