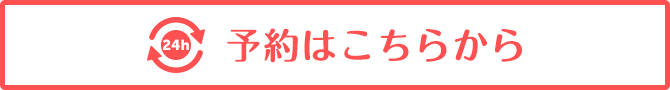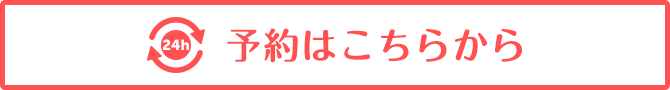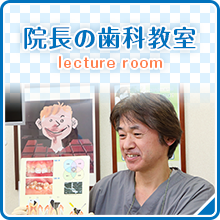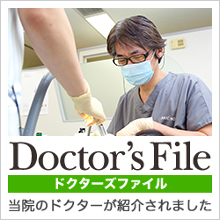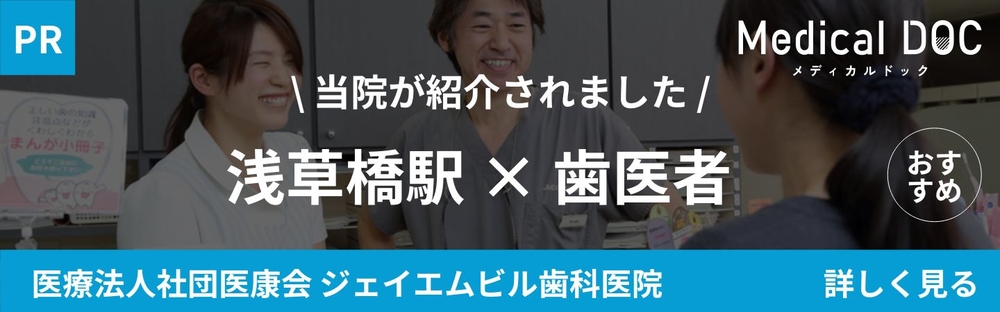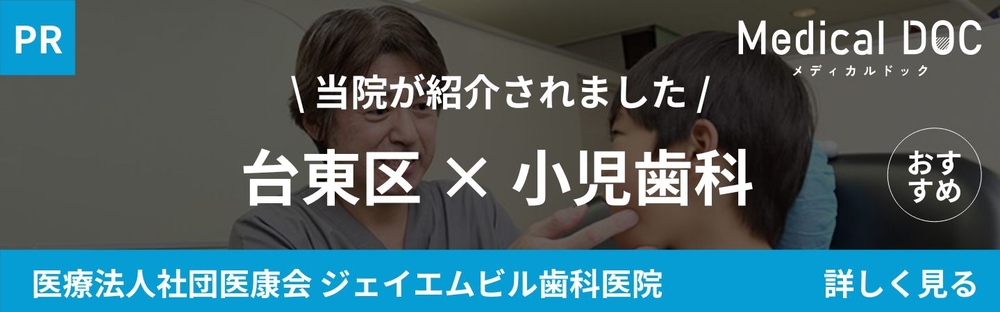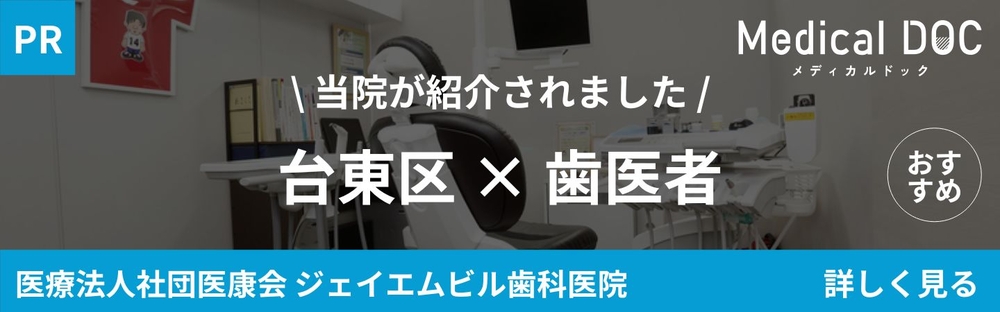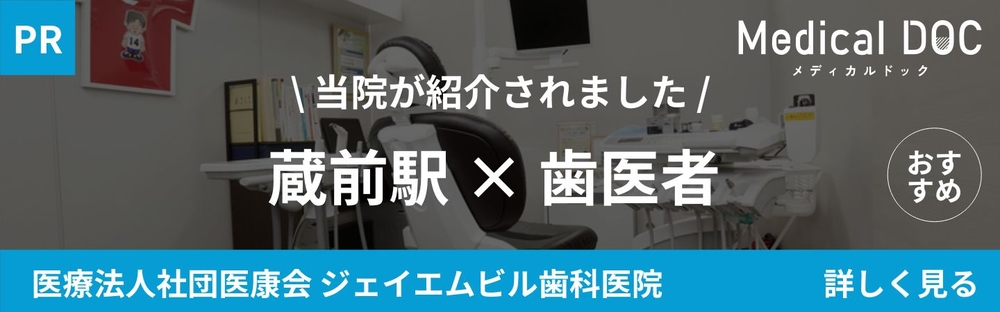1930年代米国の耳鼻科医・コステン氏が、悪い噛みあわせにより関節を支える筋肉に負担がかかり顎関節症引き起こされると発表しました。
しかし、噛みあわせが悪くても無症状であったり、噛みあわせを調整しても症状が改善されない人がいたりということで、今にちでは、噛みあわせが顎関節症の唯一の原因であるという説は、否定されています。
新たな考えとして、日常生活や器質的な色々な要因が重なり顎関節や周囲の筋肉に負担がかかり、それに耐えられなくなった時、発症するという複数因子説が支持されています。
たとえば、精神的ストレス・就寝中の歯ぎしり・スポーツなどによる外傷・食習慣などが挙げられますが、その患者さんによっておかれている状況が違いますので、それらを正しく把握する事は、とても困難なことであり原因の特定が難しいため、私の経験では、対症療法に止まる事が多く見られます。
歯医者の領域としては、常識ですが何もしないときの上下の歯は、接触しておらず食物の咀嚼や嚥下・会話の時に瞬間的に触れ合うだけなのです。
しかし、最近では、ある大学病院で研究が進み、何もしないときにも上下の歯が強く接触している人がいることが分かりました。
上下の歯を軽く接触させる動きだけでも、口を閉じる筋肉は活発に活動し、この時間が長くなればなるほど筋肉は疲労を起こし、同時に、長時間、顎関節にとっては予期せぬ力が加わり圧迫された状態になり血流が悪くなる事により関節に痛みを感じやすくなるそうです。
例えると、長時間正座をしていると足がしびれてしまうのと同じです。そして、この上下の歯を無意識に接触させている人が、顎関節症を持っている人の8割近くに及ぶことが明らかになり、とくに、精密な作業に携わるひとは、この傾向が強いそうです。
顎関節治療では、この有害な運動をコントロールするための筋肉と関節のリハビリを優先して行うことで従来の治療法より効果が上がり、治療期間の短縮がみられるとのことです。
この概念は、私たち歯科医にとっても新しく、治療法に関してもこれから発展するとのことですので、勉強していきたいと思います。
私が長年行っている顎関節症治療は、マウスピースを使ったり、ストレッチと合わせて関節にレーザーを当て疲労を軽減したりというもので、良い効果を上げていますが、一方では、治りきらずに高次医療機関を紹介する事もありました。
この新しい理論に注目したいと思います。
難しい顎関節症に対応できるよう学びたいと思います
医院案内は、こちらです。
蔵前 ジェイエムビル歯科医院
院長 野崎康弘