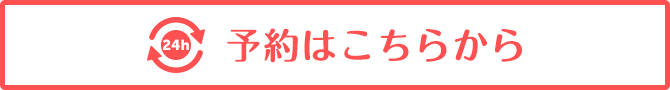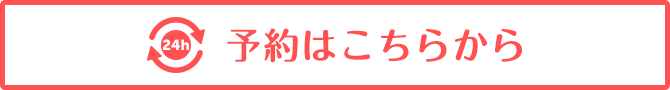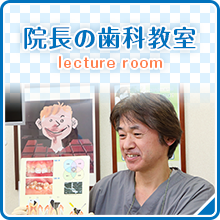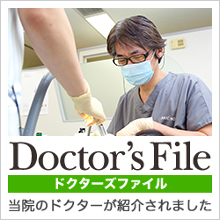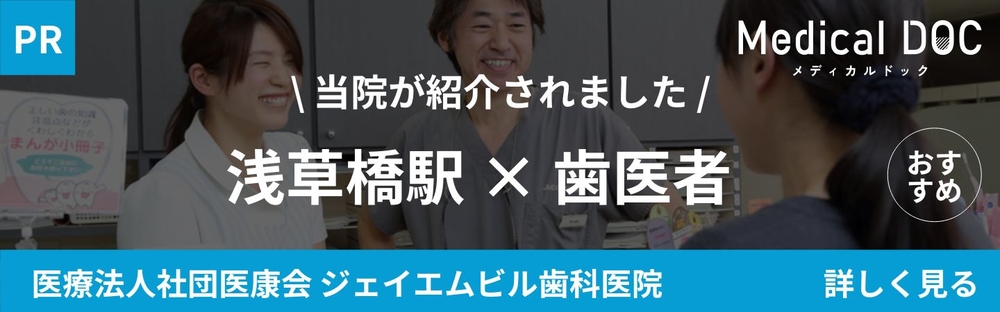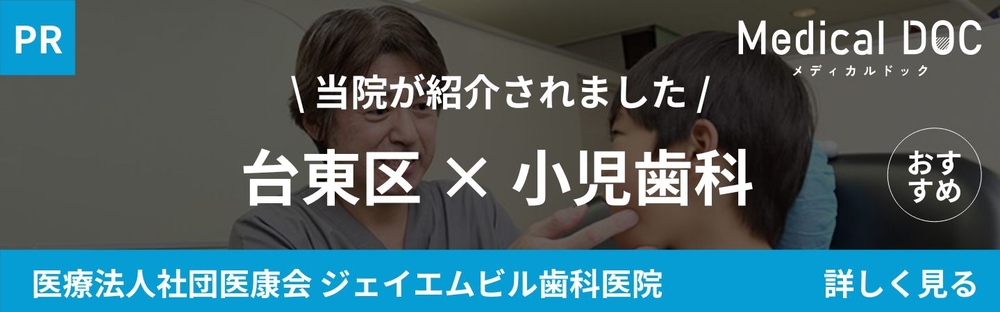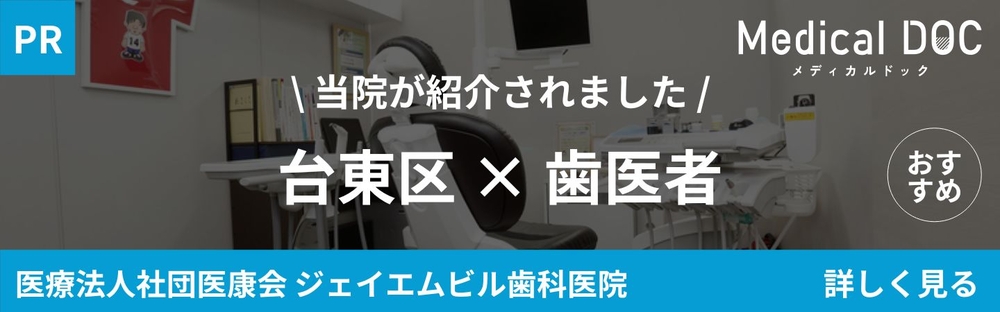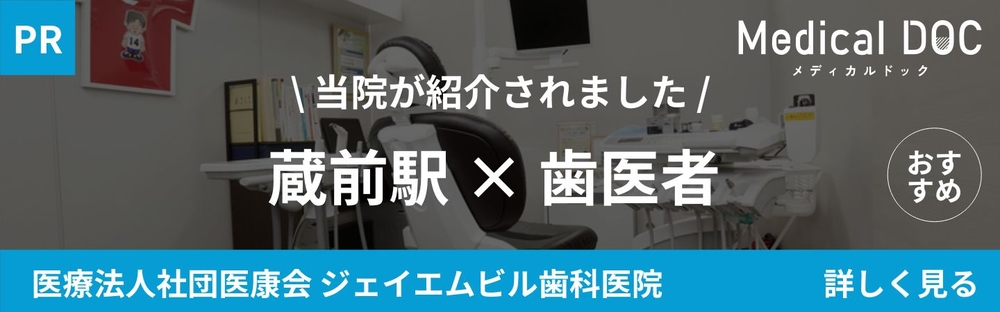と思われるかもしれませんが、学校健診において6歳で約40%・9歳で約60%歯肉炎が認められるとの報告があります。
歯肉炎とは、歯肉に限局した炎症で歯を支える骨の破壊や歯周ポケットと呼ばれる歯と歯茎のすきま深くには、炎症が、進んでいないもの言います。一方、歯周病は、歯を支える骨などに炎症が波及したものを言います。
殆どの場合、不潔性歯肉炎と呼ばれ正しいブラッシングが出来ていないことにより細菌性プラークが歯と歯茎の境目に蓄積したことが原因です。
特に小学生では、幼児期と違いご両親がお子さんの仕上げ磨きをやめる時期でお子さんの自己管理が大切でありブラッシングを習う必要があります。
そして、この時期は、混合歯列期といわれる乳歯と永久歯が入り混じり、その時期によりブラッシング方法を変えたりする必要がありますので、定期的に歯医者で指導を受けることお勧めします。
また、お子さんによっては、叢生といって永久歯が重なって生えたりすることがあり、矯正も視野に入れた予防対策が大切です。
全身的因子として中学生以降の体の生理的変化による影響で歯肉の感受性が敏感になり、比較的プラークコントロールが良好な状態でも思春期性歯肉炎が生じることがあります。
この時期のお子さんは精神的に不安定なことが多くブラッシングが疎かになりがちで思春期性歯肉炎を増悪させてしまうこともあります。
歯肉炎は、放置しますと歯肉だけの表面的な炎症に止まらず歯を支える骨にまで炎症がおよび歯周病へと移行することがありますので、歯ぐきから血が出るなどの症状があるお子さんは、早目に歯科を受診しましょう。
最近では、小学生でブラッシング時に出血したりという傾向が見られますが、定期健診を欠かさず受けることで殆どが歯周病へ移行せずにすむことが多いようです。
「歯科疾患実態調査」の中の「歯みがき行動」の調査では、毎日歯を磨く人、一日3回歯を磨く人の数は、年々増加しているにもかかわらず、中学生~高校生・成人にかけての歯周疾患の罹患率は増えています。、このことは、「磨いてはいるけれど、多くの人は、正しいブラシングが身に付いておらず、自己流のブラッシングであり、十分な歯周病予防効果を上げていない」という表れと思います。
歯肉炎に関するお子さん自身や保護者の方の関心は、虫歯に関するものと比べると低いのが現状です。将来、歯周病にかからないようにするためには、小児期の歯肉炎を放置しないことが望まれ、私たち歯科医も「小児期の歯肉炎の怖さ」を訴えてゆくことが大切であると思います。
正しいブラシングを習い、歯肉炎とお別れしましょう!
歯周病治療の詳細は、こちら
蔵前 ジェイエムビル歯科医院
院長 野崎康弘